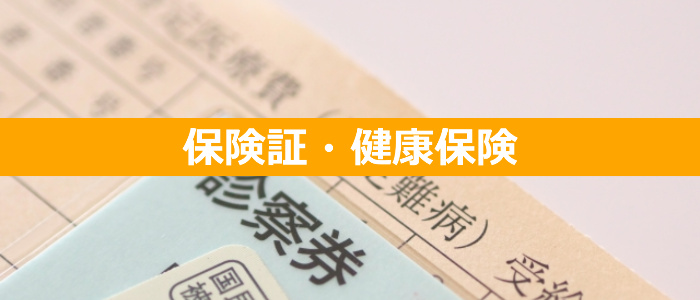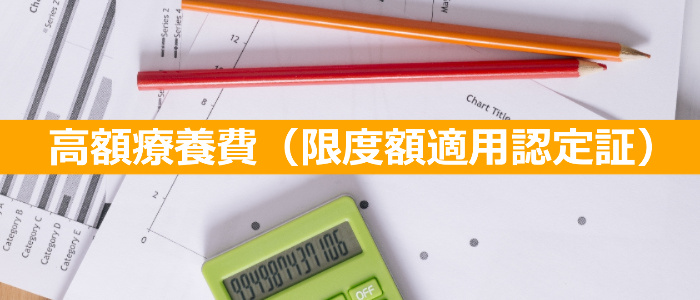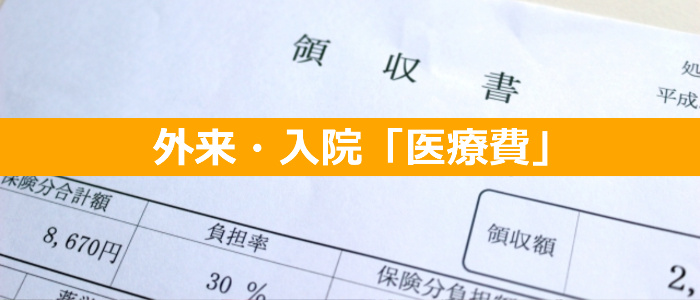限度額適用認定証は、患者さん本人が入院中の場合、基本的に患者さんご家族の方にお手続きをお願いしています。
ただ、患者さんご本人が一人暮らしなど、ご家族や頼れる親族、親戚が近くにいらっしゃらないこともあります。ではそのとき、入院中患者さんは、限度額適用認定証の申請をどうしたらよいのか?不安になりますよね。
でも大丈夫です。入院中でも限度額適用認定証の申請はできます。
患者さんの状態によって、できること、できないこと、色々とあるとは思いますが、看護師や事務など病院スタッフの手を借りながら申請してみてください。
一番手っ取り早い方法は、4つめにご紹介する「直接健康保険にお問い合わせすること」です。↓下のリンクをタップして、ここからお読みください。
→「直接健康保険にお問い合わせする」はこちら
この記事では、入院中患者さんご本人が限度額適用認定証の手続きをする方法をまとめていきます。
【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。
→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。
2026年度、医療費が値上がりします。

健康保険の公式サイトから申請書をダウンロードして限度額適用認定証を申請する。
入院中に患者さん本人が限度額適用認定証の申請をする方法、その1は、健康保険の公式サイトから限度額適用認定証(高額療養費)の申請書をダウンロードして、健康保険に申請書を郵送することです。
公式サイトで申請書をダウンロードできる健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や、板金国保などがあります。板金国保とは、全国板金業国民健康保険組合(全板国保)のことです。
申請書をダウンロードできる健康保険は、公式サイトに掲載して無料ダウンロードできるようになっています。「○○健康保険(←ご加入の健康保険名) 申請書 ダウンロード」などで検索すると、大抵、検索結果にでてきます。
スマホでダウンロードして、入院している病院のコンビニのマルチプリンターで印刷することになります。封筒や切手なども、ついでに買っておくと1回で全て用意できますね。
また、限度額適用認定証の申請書が、健康保険の公式サイトなど、インターネット上に公開されているようでしたら、病院の事務やクラークに「申請書を印刷してもらえないか?」聞いてみることもひとつの方法です。
限度額適用認定証が早く届いて、患者さんの入院費を安くできる。結果、患者さんに入院費をお支払いいただけるのであれば、病院もそのくらい協力してくれることがあります。
封筒や切手は、コンビニや売店になければ事務に頼めば送ってくれることもあります。「封筒代50円、切手代110円かかりますがよろしいですか?」など、聞かれるかもしれませんが、コンビニで自分で買ってもかかる費用なので同じことです。
入院費の請求書に含まれるのか、封筒代や切手代だけ別でいま支払いなのか、確認しておきましょう。
病院のコンビニで印刷できるならコンビニで印刷する、封筒や切手もコンビニで購入することは、「治療とは関係ない。患者さんご自身でやってください。」として断られることもあります。
しかし、「そのくらい、いいですよ~。」と申請書を印刷して、郵送しておいてくれる病院もあります。(印刷代、封筒代、切手代は自費で請求されるかもしれませんが。)
限度額適用認定証の申請書1枚でも、病院によって対応が様々なので、入院している病院の事務やクラークにお尋ねください。
コンビニのネットプリントで申請書を印刷して限度額適用認定証を申請する。
入院中に患者さん本人が限度額適用認定証の申請をする方法、その2は、ネットプリントで限度額適用認定証(高額療養費)の申請書をダウンロードして、健康保険に申請書を郵送することです。
ネットプリントは、セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどのコンビニにある、マルチプリンターに番号を入力して、登録されているデータ(申請書)を印刷できるものです。
ネットプリントで限度額適用認定証の申請書を印刷できる健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や全国外食産業ジェフ健康保険組合などがあります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、セブンイレブンやローソン、ファミリーマート、ミニストップなどに対応しています。全国外食産業ジェフ健康保険組合は、セブンイレブンに対応しています。
ご加入の健康保険公式サイトで申請書番号を確認して、印刷します。「○○健康保険(←ご加入の健康保険名) 申請書 ネットプリント」などで検索すると、大抵、検索結果にでてきます。
申請書をスマホでダウンロードしてマルチプリンターで印刷するのと、ネットプリントで申請書を印刷するなら、どちらかというと、ネットプリントの方が簡単です。
どちらにしても印刷代はかかりますし、スマホにダウンロードしてマルチプリンターで印刷する場合、スマホとマルチプリンターの連携設定などもあり、手間が増えます。
ネットプリントなら申請書データが登録されていますので、申請書番号さえ間違えなければ欲しい申請書を確実に印刷できます。
職場、勤務先に入院中の限度額適用認定証の申請方法をお問い合わせする。
入院中に患者さん本人が限度額適用認定証の申請をする方法、その3は、職場、勤務先に聞いてみる(確認する)です。
社会保険や、国民健康保険の中でも建設国保や板金国保などの職業別国保に加入されている患者さんは、職場や勤務先で限度額適用認定証の申請をしてくれることがあります。
会社で健康保険に加入しているので、手続きに関しても可能です。社長や事務員さん、人事課の方、所属部署の上司に聞くとわかることがあります。
上司に聞いてわからなければ、「それは人事課がわかる。」など、どこに聞けばいいのかを指示してくれます。
入院中の場合は、事情(入院中で会社に行けない)を話して、上司に代わりに頼んでみると、上司から人事課に行き、申請してくれることもあります。
上司がやってくれないときは、人事課に電話を転送してもらうか、人事課直通電話番号を聞いて、自分で人事課に事情を話したり、限度額適用認定証の申請を頼むこともあります。
小さい会社、社員さんが少ない会社は社長が全てやっている会社もありますので、健康保険(保険証)の手続きを社長がしてくれた会社では、社長に聞いてもわかります。
または、職場と病院で直接やりとりして、限度額適用認定証を申請できる場合もあります。私は以前に建設会社の事務員さんと電話して、入院患者さんの限度額適用認定証が発行されたことがありました。
職場と病院がお互いに個人情報を保持しようとしたら話が進みませんので、入院患者さんは病院の事務付近で待機して、本人承諾をした上で、電話等、連絡していただけると助かります。
会社によって、やり方や担当部署など様々なので、直属の上司や事務員さん、社長にお問い合わせください。
入院中の限度額適用認定証の申請方法を健康保険に直接お問い合わせする。
入院中に患者さん本人が限度額適用認定証の申請をする方法、その4は、ご加入の健康保険に聞いてみる(確認する)です。
- 患者さんが自分で動けること。
- スマホやマルチプリンターを操作できること。
- 加入している健康保険が公式サイトに申請書データを公開していること。
- 入院している病院にマルチプリンターがあること。
- 加入している健康保険がネットプリントに申請書データを登録していること。
- 入院中のコンビニのマルチプリンターが健康保険の指定ネットプリントであること。
申請書をダウンロードして印刷したり、ネットプリントで申請書を印刷するには、これらの条件をクリアする必要があるため、患者さんの状態や入院中の病院、ご加入の健康保険によっては申請書印刷をできないこともあります。
また、職場や勤務先に聞いてみるといっても、職場に入院の詳細を知られたくなかったり、仕事を増やして迷惑かけたくないということもありますよね。
いろんな状況や事情によって、どうしようもないときには、ご加入の健康保険に直接お問い合わせする方法もあります。
限度額適用認定証の発行は、健康保険のサービスのひとつで、保険証を発行するように、限度額適用認定証を発行してくれます。
職場や勤務先に頼んでも、健康保険が限度額適用認定証を発行して、会社を通して、患者さんご本人のお手元に届きます。なので、健康保険に限度額適用認定証の申請を確認することは、会社(職場や勤務先)を省略することでもあります。
「入院中で会社に行ったり、申請書をダウンロードしたりできないのですが、限度額適用認定証の申請をしたいです。どうしたら良いですか?」という内容を、健康保険に直接お問い合わせします。
すると、「申請書を病院宛てに送ります。」「電話でお受けします。」など、入院中という患者さんの状況を考慮した上で、限度額適用認定証の申請方法を提案してくれます。
たとえば、全国健康保険協会は、申請書と一緒に折って封筒にできる用紙も同封してくれるので、非常にありがたいですね。こちらの記事で詳しく書いていますので、合わせてご覧ください。
→全国健康保険協会に限度額適用認定証の申請書類を送ってもらいたい患者さんはこちら
限度額適用認定証が間に合わなかった場合、入院中に申請できなかった場合の対処方法。
入院中に限度額適用認定証を申請しようとしたけど、病院の提出期限に間に合わなかった場合。また、なんらかの事情で限度額適用認定証の申請ができなかった場合。そういうときには、他の方法で高額療養費を利用できます。
○○市や○○町など、市町村の国民健康保険は、「委任払い」という申請方法があります。病院で申請書や委任状を記入することで、3割負担の入院費を高額療養費の限度額までに抑えることができます。(限度額適用認定証を似ています。)
全国健康保険協会は、高額療養費の8割分を無利子で借りる「高額医療費貸付制度」を利用できます。還付手続きしたとき、払い戻しされるお金を一部前払いしてもらうイメージです。少々ややこしいので、こちらの記事でゆっくりご確認ください。
→全国健康保険協会の「高額医療費貸付制度」について、詳しくはこちら
また最終的には、「還付手続き(償還払い)」で高額療養費を使えます。一度3割負担で病院にお支払いいただき、後で健康保険に申請することで限度額以上のお金を高額療養費として払い戻ししてもらう方法です。
還付手続きであれば、どなたでも、どの健康保険でも利用できますし、2年以内ならいつでも申請可能です。患者さんの自己負担限度額は、限度額適用認定証を使ったときと同じになりますので、還付手続きもぜひご利用ください。
→高額療養費の「還付手続き(償還払い)」について、詳しくはこちら
この記事が入院患者さんのお役に立てれば幸いです。
保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。
スポンサーリンク