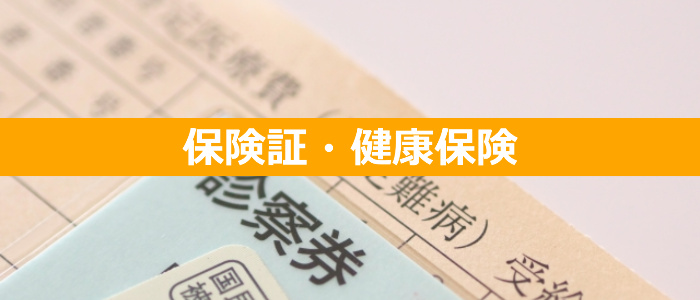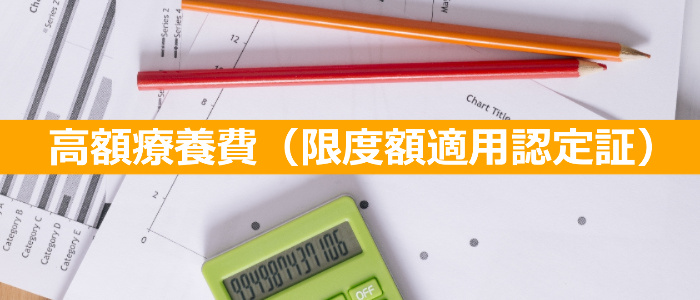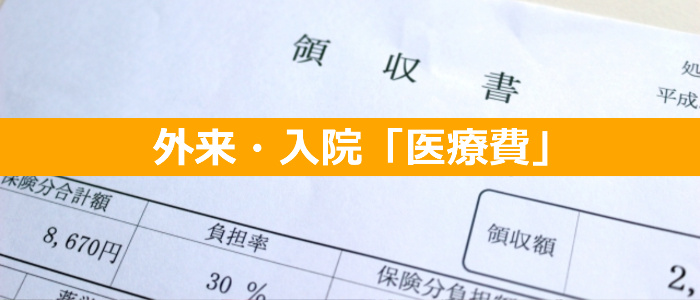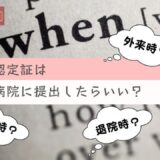病院での検査や治療で高額療養費(限度額適用認定証)を使ったけど、調剤薬局ではお薬が1種類出ただけで全然高額にならなかった。
逆に、病院では診察して終わったけど、病院の医療費よりも院外処方でもらう調剤薬局(お薬代)の方が高くなることがありますね。
大丈夫です。お薬代(調剤薬局)分も、高額療養費(限度額適用認定証)の対象になります。
処方された病院の医療費として計算されますので、病院と調剤薬局を合わせて限度額までの自己負担額にすることができます。
病院と調剤薬局を合わせて、高額療養費の限度額までにする場合は、ご加入の健康保険で還付手続きが必要です。
調剤薬局での高額療養費、限度額適用認定証について、事例を交えながらご説明します。
【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。
→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。
2026年度、医療費が値上がりします。
調剤薬局のお会計にも高額療養費(限度額適用認定証)を利用できます。
お薬代、調剤薬局の会計にも、高額療養費(限度額適用認定証)を使えます。
たとえば、がんや難病の患者さんは、病院での診察代よりも院外処方でもらう薬代(調剤薬局)の方が高くなることがあります。
- 外来医療費、1,000円
- 調剤薬局代、90,000円→高額療養費(限度額適用認定証)で、80,430円。
という場合、調剤薬局のお支払いで、高額療養費を利用できます。(※高額療養費の区分ウの場合。)
調剤薬局で限度額適用認定証を使って、80,430円になります。
9,570円の負担減なので、これだけでも十分ではありますが、さらに病院の外来費と合わせて高額療養費を使うこともできます。
調剤薬局の80,430円に、病院の外来医療費1,000円を合わせると、81,430円。ここに高額療養費の計算をやり直すと、80,463円になります。
3割負担で合計91,000円だった病院代、お薬代が、高額療養費で80,463円になります。差額の10,536円は大きいですよね。
ちなみに、限度額適用認定証は使っても使わなくても、高額療養費(還付)の手続きをすれば、患者さんの自己負担金額は同じ(80,463円)になります。
- 【限度額適用認定証を使用する】場合。
- 外来医療費、1,000円
- 調剤薬局代、90,000円→高額療養費(限度額適用認定証)で、80,430円。
- 外来費(1,000円)+薬局代(80,430円)=81,430円→高額療養費(還付手続き)で、患者さん自己負担金額80,463円。
- 967円、後日払い戻し(返金)されます。
- 【限度額適用認定証を使用しない】場合。
- 外来医療費、1,000円
- 調剤薬局代、90,000円(高額療養費(限度額適用認定証)を使わない。)
- 外来費(1,000円)+薬局代(90,000円)=91,000円→高額療養費(還付手続き)で、患者さん自己負担金額80,463円。
- 10,537円、後日払い戻し(返金)されます。
調剤薬局の料金は処方された病院の医療費に含めて高額療養費の限度額までにできます。
高額療養費は「調剤薬局の料金、医療費は、処方された病院の医療費に含まれる。」という考え方です。
なので、「病院代で高額療養費の限度額になっている。だけど調剤薬局の料金は少なかった。」という場合も対象になります。
たとえば、「病院の外来で抗がん剤治療をしたので、高額療養費の限度額まで医療費がかかった。調剤薬局では痛み止めだけもらったから少額だった。」というときも、病院代に調剤薬局の分も合わせて高額療養費を利用することができます。
上記を実際に計算してみますね。先程の金額、病院と薬局を入れ替えただけです。
- 外来医療費、90,000円→高額療養費(限度額適用認定証)で、80,430円。
- 調剤薬局代、1,000円
病院の外来費は、抗がん剤治療をして、90,000円になりました。でも限度額適用認定証の区分ウで、80,430円になった。ここまではいろんなサイトでもよく説明されていますよね。
このあと、帰りに調剤薬局で痛み止めの薬をもらって、1,000円だった。
高額療養費は2つ以上の病院や調剤薬局を合わせるとき、病院や調剤薬局、1箇所あたり21,000円以上になっていることが条件のひとつです。
ですが、「調剤薬局の分は、処方された病院の医療費に含める。」という考えもあります。この場合、20,000円未満でも、処方された病院の医療費が限度額以上になっていれば、調剤薬局も高額療養費の対象になる。ということです。
よって、病院の外来費と調剤薬局分を合わせて、高額療養費の計算をやり直すと、80,463円になります。
限度額適用認定証の使用については、病院で使う使わないに関係なく、患者さんの自己負担金額は変わりません。ご安心ください。
- 【限度額適用認定証を使用する】場合。
- 外来医療費、90,000円→高額療養費(限度額適用認定証)で、80,430円。
- 調剤薬局代、1,000円
- 外来費(80,430円)+薬局代(1,000円)=81,430円→高額療養費(還付手続き)で、患者さん自己負担金額80,463円。
- 967円、後日払い戻し(返金)されます。
- 【限度額適用認定証を使用しない】場合。
- 外来医療費、90,000円(高額療養費(限度額適用認定証)を使わない。)
- 調剤薬局代、1,000円
- 外来費(90,000円)+薬局代(1,000円)=91,000円→高額療養費(還付手続き)で80,463円。
- 10,537円、後日払い戻し(返金)されます。
病院と調剤薬局を合わせて高額療養費を使うには「還付手続き」をします。
病院、または調剤薬局で医療費が高額になったら、限度額適用認定証を提出すれば安くすることができます。
ですが、限度額適用認定証で、病院と調剤薬局を合わせて高額療養費の計算することはできないのです。そこは、病院は病院、薬局は薬局、ですね。
そのため、病院と調剤薬局と合わせる場合、高額療養費の還付手続きをする必要があります。こちらですね。
- 【限度額適用認定証を使用する】場合。
- 外来医療費、1,000円
- 調剤薬局代、90,000円→高額療養費(限度額適用認定証)で、80,430円。
- 外来費(1,000円)+薬局代(80,430円)=81,430円→高額療養費(還付手続き)で80,463円。
- 967円、後日払い戻し(返金)されます。
- 【限度額適用認定証を使用しない】場合。
- 外来医療費、1,000円
- 調剤薬局代、90,000円(高額療養費(限度額適用認定証)を使わない。)
- 外来費(1,000円)+薬局代(90,000円)=91,000円→高額療養費(還付手続き)で80,463円。
- 10,537円、後日払い戻し(返金)されます。
病院と薬局、両方で限度額になっていたとしても、限度額適用認定証を使う場合、窓口ではそれぞれで限度額までお支払いをして、後日ご加入の健康保険で高額療養費の還付手続きをします。
- 【限度額適用認定証を使用する】場合。
- 外来医療費、90,000円→高額療養費(限度額適用認定証)で、80,430円。
- 調剤薬局代、90,000円→高額療養費(限度額適用認定証)で、80,430円。
- 外来費(80,430円)+薬局代(80,430円)=81,430円→高額療養費(還付手続き)で83,430円。
限度額適用認定証は使った方がいいのか、使わない方がいいのか、よくご質問をいただきますが、どちらでも大丈夫です。高額療養費の還付手続きをすれば、最終的に患者さんの自己負担金額は同じになりますので、ご安心ください。
私個人的には、患者さんの自己負担金額は変わりませんし、一時的なお支払いでも患者さんの金銭的な負担が減るため、面倒でも高額療養費制度の手続きをしておくことをおすすめします。
外来費と薬局分を合算するときは?全国健康保険協会の申請書類書き方。
外来医療費と調剤薬局代金を合算するときの申請書類について、協会けんぽを例にご説明します。
加入してる健康保険が全国健康保険協会の場合、「健康保険 被保険者、被扶養者、世帯合算 高額療養費 支給申請書」になります。
書類は申請内容に調剤薬局の分も1病院として記入します。なので、外来医療費と調剤薬局代金の2項目埋まることになります。
名称や住所、金額を変えるだけで、病名や期間は同じでOKです。
高額療養費の計算は病院の外来費用と調剤薬局の料金を足して計算されますので、ご安心ください。
くわしい還付手続きの記入例はこちらにあります。
→全国健康保険協会の還付手続き申請用紙。本人の書き方はこちら
→全国健康保険協会の還付手続き申請用紙。家族の書き方はこちら
市町村の国民健康保険にご加入の患者さんは、区役所や市役所、町村役場に行くと還付手続きができます。病院と調剤薬局の領収書、払い戻しのお金を振り込んでもらう銀行口座がわかるもの(通帳など)、印鑑を持っていってください。
その他の健康保険の患者さんは、ご加入の健康保険、または職場の上司、人事課や総務課など、健康保険の手続きをしている担当者さんにご確認ください。
保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。
スポンサーリンク