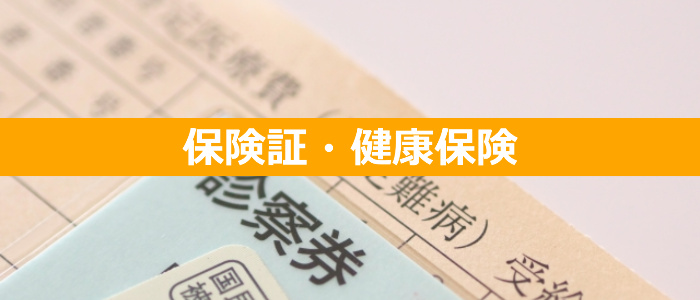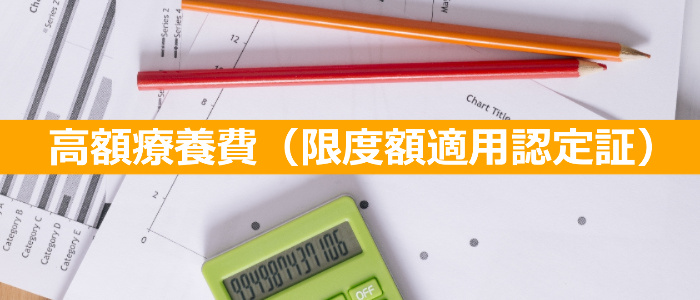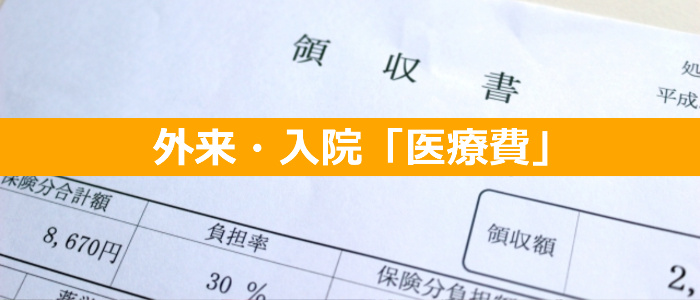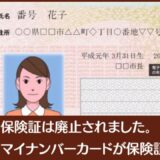「入院中の病院ではできないので、他院受診することになった。」という患者さんの医療費は、3割負担か0円になります。
当ブログでよくあるご相談としては、「自費(10割)請求になる」ということでした。ですが私の調査と経験上、「他院受診した医療費は健康保険適用になる。」。
さらに、「外来受診先の病院医療費は、3割負担でのお支払いか、0円(患者さんのお支払いなし)になる。」ということです。
入院した病院や病棟、患者さんによって、3割負担になるか、0円でお支払いがなくなるか、どちらになるかは、そのとき、その状況にならないとわかりません。しかし、はっきりしていることは「自費(10割負担)になることはない」ことです。
この記事では、他院受診した医療費はいくらになるのか、どういう仕組みになっているのか、解説していきます。
2026年度、医療費が値上がりします。

入院中の他院受診は、入院している病院の計算方法が「出来高」か「DPC」かで変わります。
入院中の病院ではできない検査や治療のため、他の病院に行くことになった患者さん。
入院している病院の計算方法が「出来高計算」か「DPC計算」かで、入院中の他院受診もお支払いが決まります。
DPC対象の病院や病棟でも出来高計算になる病名の患者さんは、出来高計算の病院や病棟の患者さんとして、入院中の他院受診を考えます。
さてでは「他院受診分の医療費を、誰がいくら払うのか?」、厚生労働省はこのように決めています。解説していきますね。
出来高計算の病院や病棟に入院中の患者さんは、他院受診先でのお支払いが3割負担か0円になる。
他院受診先で、患者さんのお支払いが3割負担(自己負担額)になる場合。
(2) 入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。(令和6年診療報酬点数表 第2部入院料等 通知<通則>「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」より一部抜粋)
「出来高計算の病院や療養病棟などの患者さん」についてはこちら。※出来高計算は、検査やレントゲン、お薬や点滴など、行われた医療行為が積み重なっていく計算方法です。
わかりやすく書きますと、
「入院患者さんが必要があって別の病院を受診したとき、受診した別の病院の医療費は、そのまま受診した別の病院で計算しましょう。」
というようになります。
例えば、A整形外科に足を骨折して入院している患者Bさん。高血圧の持病があり、C内科に通院して薬をもらっています。
A整形外科では処方できないお薬だったので、C内科と調剤薬局まで、患者さん(ご家族の方)に取りにいってもらいました。そのとき、C内科や調剤薬局で、そのまま3割負担でお支払いしてください。
というものです。
他院受診先で患者さんのお支払いが0円になる場合。
ですが、出来高計算の病院や病棟に、入院中に他院受診として行くと、場合によっては医療費が0円になることもあります。それは厚生労働省の決まりでこのようなことがあるからです。
(6)エ 他医療機関において当該診療に係る費用を一切算定しない場合には、他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において算定し、入院基本料等の基本点数は控除せずに算定すること。この場合において、入院医療機関で算定している入院料等に包括されている診療に係る費用は、算定できない。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。(令和6年診療報酬点数表 第2部入院料等 通知<通則>「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」より一部抜粋)
こちらは赤文字部分をわかりやすくすると、
「他院受診先で請求しないときは、入院中の病院で計算してください。」
ということになります。
たとえば、急な腹痛で近くの総合病院に緊急入院した患者さん。眼科に定期的に通院中です。
もうすぐ薬がなくなりそうでしたが、入院した総合病院には眼科がなく、点眼薬の処方はできない。なので、通院中の眼科まで点眼薬を取りにいってもらいました。
このとき、患者さんにはお支払いをしない(0円)でください。眼科でかかった医療費は入院中の病院でやったことにして、入院中の病院代に含めて計算してください。
というものです。
出来高計算の病院や病棟で、患者さんのお支払いが3割負担か0円か、どちらかになる理由。
出来高計算の病院や病棟に入院した患者さんが、他の病院に行くとき、他院受診先での患者さんのお支払いは「3割負担」か「0円(お支払いなし)」のどちらかになります。
→3割負担か0円かどちらかになる理由をスキップするには、ここをタップしてください。
それは厚生労働省が入院中の病院に、こういった決まりを言っているからです。↓
ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。
イ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の40%を控除した点数により算定すること。
ウ 入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を算定しない場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。
(令和6年診療報酬点数表 第2部入院料等 通知<通則>「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」より一部抜粋)
この決まりをわかりやすく言うと、
「入院中の患者さんが別の病院を受診したら、別の病院を受診した日の入院料(ベッド代など)を5%~40%低くしなさい。」
ということです。
たとえば、1日の入院料が15,000円だった場合、他院受診をした日の入院料を10%低くする。ということは病院は-1,500円の収入減になります。
そこで他院受診先の医療費によって、3割負担にするか、0円にするのかを決めるのです。
このページでは1日の入院料が15,000円、他院受診した日は-10%(-1,500円)にする。として、他院受診先の医療費が1,000円だった場合と2,000円だった場合で解説しますね。(本来は点数で計算しますが、ここでは全て円で計算します。)
以下の表を参考に、解説をご覧ください。
| 入院中の病院の収入と支出 | 他院受診先の医療費 | 入院中の病院の最終的な収入と支出 |
| +1,500円 | -1,000円 | +500円 |
| -1,500円 | 0(+2,000円) | 0(+500円) |
他院受診先の医療費が入院中の病院の1日の入院料よりも低い場合、入院中の病院では10%引かないでそのまま計算します。そして他院受診先の医療費は入院中の病院が10割負担でお支払いします。すると、入院中の病院では差し引き後、+500円になります。
+1,500円-1,000円=+500円
他院受診先で患者さんに3割負担で支払ってもらうと、入院中の病院が-10%(-1,500円)になるので、10割負担することで、少し(+500円)でもプラスになるのなら、入院中の病院が10割負担します。だから患者さんの他院受診先でのお支払いは0円になります。ということです。
逆に、他院受診先の医療費が入院中の病院の1日の入院料よりも高い場合、入院中の病院では10%引いて、他院受診先で患者さんに3割負担でお支払いしてもらいます。入院中の病院で-1,500円引くだけで、他院受診先の医療費は入院中の病院にとって0円なので、損はない。
他院受診先の医療費を入院中の病院が10割負担したところで、1円もプラスになりません。それどころか、1日の入院料は+1,500円の収入になったとしても、他院受診先の医療費が-2,000円になり、最終的には-500円になります。
+1,500円-2,000円=-500円 → -1,500円+0円=-1,500円
他院受診先で患者さんに3割負担で支払ってもらうことで、入院中の病院で-10%(-1,500円)のマイナスで済みます。考え方によっては、入院中の病院は少し(-500円)でも出費を抑えられる。なので、患者さんの他院受診先でのお支払いは3割負担になります。ということです。
出来高計算の病院や病棟に入院中の患者さんは、他院受診先の医療費が、入院中の病院の1日の入院料よりも、高いのか、低いのか。で他院受診先でのお支払いが3割負担になるのか、0円になるのかが決まります。
DPC計算の病院や病棟に入院中の患者さんは、他院受診先でのお支払いが0円になる。
(9) DPCで入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合の他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱いとし、入院医療機関において算定すること。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。
では次は、「DPC計算の病院や療養病棟などの患者さん」についてはこちら。※DPC計算は、検査やレントゲン、お薬や点滴などの医療行為が入院料に含まれている計算方法です。
こちらをわかりやすく書くと、
「DPCで入院中の患者さんは、他院受診したとき、入院している病院でやったことにしなさい。」
ということです。
なので、出来高計算の病院や病棟とは違って、入院中の病院でできないことですが、他院受診先でのことを入院中の病院でのこととして計算します。
他院受診先でのことを入院中の病院でやったことにする理由は、DPCで入院料を計算するからです。
DPCとは、お薬や点滴、検査やレントゲンなどが入院料に含まれています。(処置や検査、手術、麻酔、リハビリなど、一部DPC入院料に含まれないものもあります。)
通常、入院中の病院でできていれば、患者さんは入院料に含まれていてお金がかからないはず。ですが、他院受診したからお金がかかってしまう。それはおかしいので、入院料している病院でやったこととして計算しましょう。
ということなのです。
DPC計算の病院や病棟に入院しているDPCの患者さんは、他の病院をした場合、他院受診先で患者さんのお支払いはなくなります。※その代わり、入院している病院の入院医療費として計算されます。
「入院中の他院受診」については、別のページもあります。こちらも参考になれば幸いです。
→入院患者の他院受診は厚生労働省が認めています。断ることはできない。はこちら
→なぜ入院中は他の病院を受診したらダメなのか?薬が欲しいだけなのに。はこちら
→入院患者が他の病院へ行く前にやること。入院中の病院でできない事か、確認。はこちら
スポンサーリンク